読書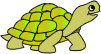 |
| 日本沈没 作者:片山左京 出版社:小学館文庫 ・上下間に分かれている文庫で呼んだ。日本のSF小説の先駆けで1970年当時に400万部も売れたと書いてあった。 この本では意外と科学的な内容がとても多かった。読む前にイメージしてたサバイバル要素はほとんどなく、地球の地質学、マントル対流の説明などが登場人物の科学者たちの言葉によって説明される。書かれている日本が高度経済成長の時代で、今の時代とは違う、と言う違和感が読んでいるとある。働いているおじさんたちが主人公。銀座のバーや、働いているおじさんたちの、仕事に対する執着とか、今とは違うなと言う雰囲気が伝わってくる。登場人物は、日本沈没に最初に気づく、科学者の田所博士、大学の助教授の幸長、情報処理の天才で仕事ができる中田、機械に精通している人(誰だっけ?)、日本の裏で力を持っている渡老人、政治に関わる官僚、日本沈没するときの海外移民に悩む総理大臣など、の頭がいい人たちが語り手になっていて、読んでいてこいつらすごいなと基本楽しい。前半は日本沈没に気づくまでの話、最初からサバイバルな展開になっていくと無意識に予想してたのとぜんぜん違った。主人公の小野寺はまだ割と若いおじさん、潜水艇技師で海を愛して、人が集まったときに起こるいざこざにはまったく興味がなく、それを避けているといってもいい。地殻変動と日本沈没の関係に気づいた田所博士に、小野寺が潜水艇士として国の元に協力していくことになる。この小野寺が、周りの、政治とか、科学者の日本沈没までの発見への道のりとか、日本沈没の際の現場の被害とかのなかで、物語を通して強いキャラを発揮する。また、他のもっとおじさんの働き手とは違う、若い新しい世代の考え方をもつ働き手としても書かれている。高度経済成長の時代、仕事とかに対する執着が強い、ただ働くしかなかった、考え方になっていた幸長は、小野寺の考え方と自分の考え方がちょっと違うな、と思ったりする。小野寺は、日本にはお世話になったし、恩は今みたいに潜水艦を操作して十分返したからもういいだろと、自分がやらなくてはいけない仕事がなくなると恋人の元に行く。損得勘定で仕事のことも割り切れる。小野寺の根底には働いて生きるという事よりも自分中にある海に対する気持ちがある。それを豊かな時代に育った若者の価値観だ、と幸長はうらやましくも思い自分とは違うなと思うけれども否定をせず、納得する。でも自分にはどうしてもそんなことはできないな、という染み付いた考え方に哀愁を感じる。 |